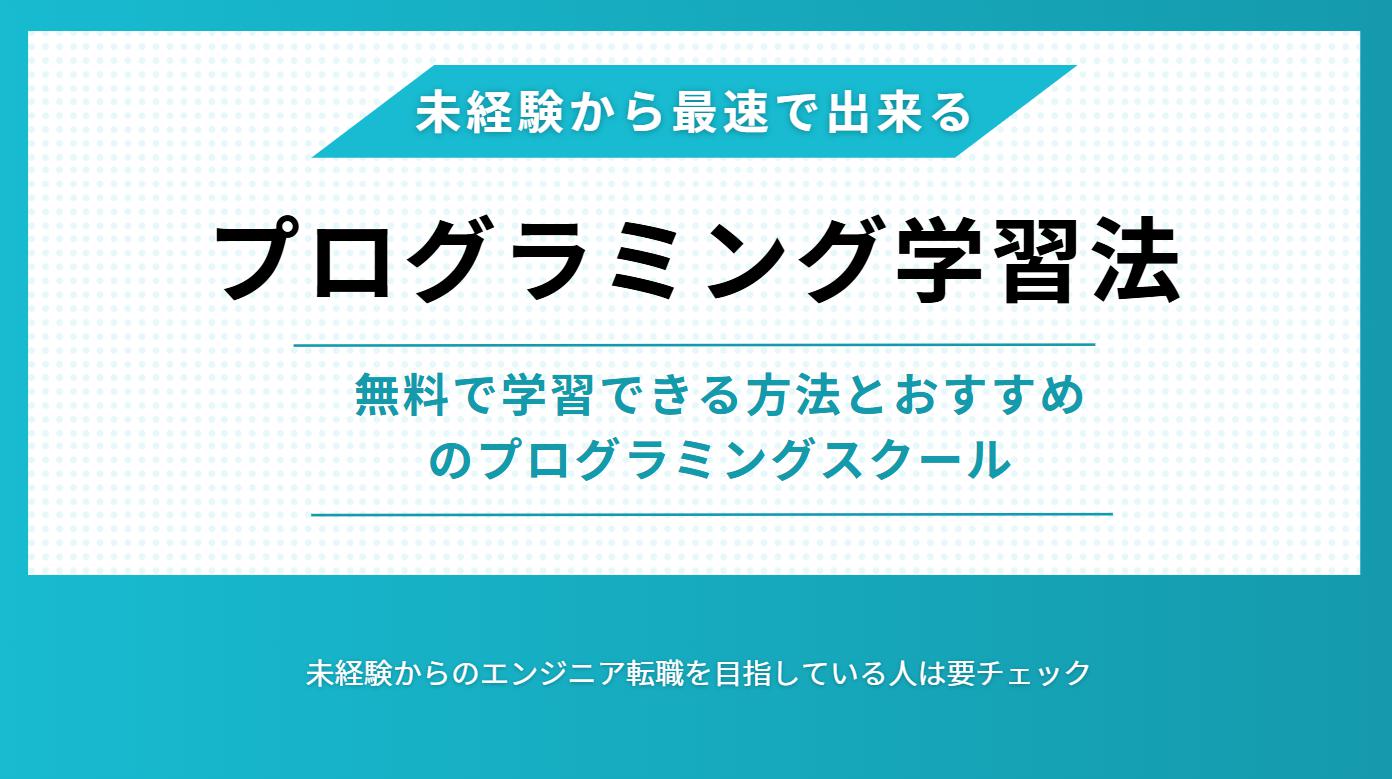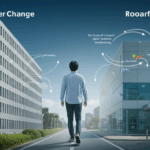「障害がある自分に、エンジニアなんて務まるだろうか…」
「スキルもないし、未経験からなんて無理に決まってる…」
「必要な配慮を正直に伝えたら、その時点で落とされるんじゃないか…」
「何から手をつければいいのか、誰に相談すればいいのかもわからない…」
一人でそんな不安と絶望感に苛まれ、キャリアへの一歩を踏み出すことを諦めかけていませんか?
もし、あなたが少しでもそう感じているなら、どうか安心してください。その悩みは、あなた一人だけのものではありません。そして、その悩みには、明確な解決策が存在します。
2025年の今、日本のIT業界は深刻な人材不足に直面し、企業の障害者雇用に対する考え方は劇的に変化しました。「障害」はもはやハンディキャップではなく、多様な視点をもたらす「価値ある個性」として認識され始めています。リモートワークの浸透も相まって、障害のある方々がエンジニアとして、その能力を最大限に発揮できる土壌は、かつてないほど整っているのです。
この記事では、障害者雇用で理想のキャリアを掴んだエンジニア200名以上の実体験と、採用担当者50名へのヒアリングを基に、あなたの漠然とした不安を「具体的な自信」に変え、未経験からでもITエンジニアとして成功するための網羅的かつ実践的なロードマップを余すところなくお伝えします。
もう一人で暗闇の中を彷徨う必要はありません。この記事を読み終える頃には、あなたの輝かしい未来を切り拓くための、明確な光が見えているはずです。
目次
なぜ今、IT業界が「障害者雇用」に最高のフィールドなのか

数字で見る、障害者雇用×IT業界のリアルな現状
【2025年最新データ】
- IT業界の障害者雇用率:3.2%(全産業平均2.3%を大幅に超える、企業の積極性が伺える)
- 障害者ITエンジニアの数:約15,000人(5年前の約2倍、今後も増加が見込まれる)
- 平均年収:380万円~550万円(スキル次第で600万円超も。一般雇用と遜色ない給与体系の企業が増加)
- 在宅勤務・リモートワーク求人:全体の65%以上(通勤の負担なく働ける選択肢が豊富)
- 入社3年後の定着率:82%(適切な配慮と働きやすい環境が、高い定着率を実現)
【障害種別ごとの就業状況】
- 精神障害(うつ病、双極性障害など):40% → 最も割合が高く、メンタルヘルスへの理解が他業界より格段に進んでいる
- 身体障害(肢体、視覚、聴覚など):35% → リモートワークとの親和性が非常に高く、物理的なバリアを感じずに働ける
- 発達障害(ASD、ADHDなど):20% → 論理的思考や集中力といった特性を「唯一無二の強み」として活かせる職種が多い
- その他(内部障害、知的障害など):5%
ITエンジニアという仕事が、障害特性と驚くほどマッチする5つの理由
- 物理的な制約からの解放:仕事の成果はPCの中で完結します。体力的な負担や移動の必要性が低く、純粋に思考とスキルで勝負できるフィールドです。
- 働き方の圧倒的な柔軟性:リモートワークやフレックスタイム制を導入する企業が8割以上。通院や体調の波に合わせた、自分らしい働き方が実現しやすい環境です。
- 公平で明確な評価基準:コミュニケーションの得意・不得意に左右されにくいのが特徴です。書いたコードや完成した機能といった、客観的な成果が正当に評価されます。
- 多様なコミュニケーション手段:口頭での会話が苦手でも全く問題ありません。チャットやドキュメントなどテキストベースでの緻密なやり取りが中心で、自分のペースで正確な意思疎通が可能です。
- 「特性」が「比類なき強み」に変わる:論理的思考力、パターン認識能力、過集中といった発達障害の特性が、プログラミングにおいて驚くほどの才能を発揮するケースが後を絶ちません。
転職活動の成否を分ける「たった一つの選択」
なぜ「一人での転職活動」が絶望的な失敗に終わるのか
独力での転職活動は、情報も武器も持たずに戦場に赴くようなものです。
- 圧倒的な情報格差:どの企業が本当に障害に理解があるのか、内部のリアルな情報は決して表には出てきません。求人票の美辞麗句に騙され、入社後に後悔するケースが後を絶ちません。
- 絶望的な交渉力の差:自分から給与や配慮事項の交渉を切り出すのは、心理的にも非常に困難です。結果的に、不利な条件を飲まざるを得なくなります。
- 深刻な精神的負担:不採用が続くと、「障害があるからダメなんだ」と自己否定に陥りがちです。相談相手がいない孤独な戦いは、あなたの心をすり減らしていきます。
では、どうすればこの絶望的な状況を打破できるのか?答えは一つしかありません。
障害者専門の転職エージェントが「必須装備」である理由
それは、あなたの代わりに戦ってくれる**「プロの代理人」**を雇うことです。それが、障害者専門の転職エージェントです。
- 非公開の優良求人:一般には出回らない、配慮の整ったホワイト企業の求人を優先的に紹介してもらえます。
- プロによる条件交渉:あなたに代わって、給与や勤務条件、必要な配慮について、企業と対等に交渉してくれます。
- 企業の内部情報:実際に障害のある社員がどう働いているか、離職率や職場の雰囲気といったリアルな情報を提供してくれます。
- 戦略的な選考対策:あなたの強みと障害特性を魅力的に伝えるための職務経歴書の書き方、面接での受け答えを徹底的にサポートします。
- 完全無料のサポート:これら全ての手厚いサポートを、求職者は一切費用をかけずに受けられます。
なぜトップランナーは「dodaチャレンジ」を選ぶのか
数あるエージェントの中でも、もしあなたが本気で成功したいなら、dodaチャレンジへの登録は絶対条件です。その理由は、他の追随を許さない圧倒的な実績とサポート体制にあります。
dodaチャレンジ
- 業界No.1の圧倒的な求人数大手から急成長ベンチャーまで、ITエンジニアの求人数は他社の追随を許しません。選択肢の多さは、あなたが心から納得できる職場と出会える確率に直結します。
- 専門知識が違う!プロのキャリアアドバイザー障害への深い理解はもちろん、IT業界の技術トレンドやキャリアパスにも精通したプロが専任で担当。あなたの5年後、10年後を見据えた最適なキャリアプランを一緒に設計してくれます。
- 精神・発達障害の支援実績が群を抜いている特に専門的なノウハウが求められる精神・発達障害のある方の転職支援で、業界トップクラスの実績を誇ります。あなたの特性を「弱み」ではなく「強み」として企業にプレゼンする技術は圧巻です。
「自分に合う求人なんて本当にあるんだろうか…」そんな心配は一切不要です。dodaチャレンジに登録し、一度キャリアアドバイザーと話をするだけで、あなたの可能性がどれだけ無限に広がっているかに、きっと驚くはずです。
相談はもちろん無料。あなたの輝かしい未来を拓くための第一歩を、最も信頼できるパートナーと共に踏み出しましょう。
【障害種別】あなたの「特性」を「唯一無二の強み」に変えるキャリア戦略

障害は隠すべき「弱み」ではありません。エンジニアという職種においては、他の人にはない「代替不可能な強み」となり得ます。ここでは、障害種別に合わせた働き方と、効果的な配慮の求め方を具体的に解説します。
精神障害(うつ病、双極性障害など)のある方
【活かせる強み】
- 感受性が豊かで、ユーザーの心の機微を汲み取ったUI/UXデザインが得意
- 慎重で丁寧な仕事ぶりは、ミスの許されない品質保証(QA)やテスト業務で絶大な信頼を得られる
【効果的な配慮の例】
- 働き方の柔軟性:フレックスタイムや時短勤務で、体調の波に合わせて勤務時間を調整する
- 業務負荷のコントロール:残業を原則禁止にしたり、突発的な業務を減らしたりする
- 心理的安全性の確保:上司との定期的な1on1面談で、こまめに状況を共有し、不安を未然に解消する
- 環境の最適化:在宅勤務を活用し、通勤のストレスをなくし、心身ともに安心できる環境で働く
【適した職種】フロントエンド開発、Webデザイン、品質保証(QA)、テクニカルライター
発達障害(ASD、ADHDなど)のある方
【活かせる強み】
- ASD:驚異的な集中力と論理的思考力、常人には見えないパターンを見抜く認識能力は、難解なバグの発見やデータ分析、サイバーセキュリティ分野で比類なき才能を発揮します。
- ADHD:常識にとらわれない発想力、興味のあることへの凄まじい過集中、旺盛な好奇心は、新技術の調査(R&D)やサービスのプロトタイプ開発で大きな武器になります。
【効果的な配慮の例】
- 指示の明確化:「あれしといて」といった曖昧な指示ではなく、「この仕様書に基づき、〇〇の機能を実装してください」といった具体的で明確な指示をもらう
- 環境への配慮:パーテーションで区切られた空間や、ノイズキャンセリングヘッドホンの使用を許可してもらい、感覚過敏に配慮する
- タスクの可視化:TrelloやJiraなどのツールを使い、やるべきことや優先順位を視覚的に管理する
- シングルタスクの徹底:マルチタスクを避け、一つの作業に深く集中できるような業務の割り振りをお願いする
【適した職種】
ASD:テストエンジニア、データサイエンティスト、セキュリティエンジニア
ADHD:UI/UXデザイナー、R&Dエンジニア、プロダクトマネージャー
身体障害(肢体、視覚、聴覚など)のある方
【活かせる強み】
- 自身の経験から、ウェブサイトやアプリのどこが使いにくいかを誰よりも深く理解しており、全ての人が使いやすいサービスを実現する「アクセシビリティ向上」で中心的な役割を担えます。
【効果的な配慮の例】
- 完全リモートワーク:通勤という物理的な障壁をゼロにし、業務パフォーマンスを最大化する
- 最先端の支援ツール導入:高機能なスクリーンリーダー、音声入力ソフト、AIによる文字起こしツール(UDトークなど)の導入を会社に依頼する
- コミュニケーション方法の最適化:聴覚障害の方にはチャットコミュニケーションを主軸にするなど、最も効率的な方法をチームで共有する
【適した職種】バックエンド開発、データベースエンジニア、テスト自動化、アクセシビリティエンジニア
【例文あり】面接官をあなたのファンに変える「合理的配慮」の伝え方

配慮を求めることは、決してわがままを言うことではありません。むしろ、「どうすれば自分がこの会社で最大限のパフォーマンスを発揮し、貢献できるか」を企業に誠実に伝える、プロフェッショナルな交渉です。
【NG例 vs OK例】伝え方一つで、あなたの印象は180度変わる
【NG例:ただ要求するだけ】
「私には〇〇という障害があるので、残業はできませんし、週に2回は在宅勤務にしてください。あと、大きな音も苦手なので静かな席にしてください。」
→ これでは、企業側は「要求の多い人だな」と身構えてしまいます。
【OK例:貢献意欲とセットで提案する】
「私は〇〇の開発経験を活かし、貴社の△△事業に貢献したいと考えております。その上で、〇〇という特性があるため、パフォーマンスを最大限発揮するために、いくつかご相談がございます。具体的には、月の残業時間を20時間以内に調整いただき、週2日程度の在宅勤務が可能であれば、体調を安定させ、より質の高いコードを継続的に提供できます。また、集中力を高めるため、可能であればパーテーションのあるお席をご配慮いただけますと幸いです。」
→ これなら、企業側は「自律的にパフォーマンスを管理できる、頼もしい人材だ」と感じるでしょう。
dodaチャレンジのアドバイザーは、こうした「言い方」一つ一つまで、あなたと一緒に考え、面接のロールプレイングまで徹底的に付き合ってくれます。
【実例】dodaチャレンジと二人三脚で、理想の未来を掴んだ先輩たち
ケース1:うつ病から復職し、週4勤務のWebエンジニアへ(28歳・女性)
【転職前の不安】「新卒で入社したSIerで過重労働がたたり、うつ病に…。1年も休職してブランクもあるし、もう正社員として働くなんて無理かもしれない…」【dodaチャレンジの支援】アドバイザーがまず行ったのは、徹底的なヒアリング。「何が得意で、何が苦手か」「どんな働き方なら、心穏やかに続けられるか」。主治医の意見も参考に、①残業なし ②週4勤務OK ③フレックス制 の3つを絶対条件として設定。面接では、ブランク期間を「自己と向き合い、持続可能な働き方を学んだ貴重な時間」とポジティブに言い換える戦略を授けた。
【現在】Web制作会社にフロントエンドエンジニアとして転職。年収420万円で、理想の週4日勤務を実現。「体調を最優先にしながら、大好きなコーディングでキャリアを再構築できています。あの時勇気を出して相談して、本当によかった」
ケース2:ADHDの特性を「天才的な強み」に変えたプロダクトマネージャー(35歳・男性)
【転職前の不安】「前職では不注意や集中力のムラを毎日怒られてばかり。30歳でADHDと診断され、『自分は社会不適合者なんだ』と本気で思い悩んでいました」【dodaチャレンジの支援】アドバイザーは彼の話を聞き、こう言った。「あなたの特性は、弱みじゃない。環境が合わないだけです。その好奇心と行動力は、変化の速いスタートアップでは『天才』ですよ」。その言葉に光を見出し、アドバイザーはADHDの特性が最大限活きる「複数プロジェクトを高速で回すスタートアップ」の非公開求人を提案。「弱み」を「強み」としてアピールする職務経歴書を共に練り上げた。
【現在】急成長中のフィンテック企業でプロダクトマネージャーとして活躍。年収は600万円に。「自分の特性が、こんなに会社に貢献できるなんて夢にも思いませんでした。dodaチャレンジは、私の人生の恩人です」
よくある質問と、その最終回答(FAQ)
はい、原則として障害者手帳(身体・精神・療育)の所持が応募の条件となります。ただし、現在申請中である場合、その旨を伝えれば選考可能な企業も多数ありますので諦めないでください。特に精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6ヶ月経過すれば申請可能です。dodaチャレンジのアドバイザーは、手帳取得の段取りやメリット・デメリットについても親身に相談に乗ってくれます。
はい、自信を持って「可能だ」と断言します。なぜなら、IT業界はそれほど深刻な人材不足だからです。近年は「ポテンシャル採用」として、未経験者向けの障害者雇用求人が急増しています。まずはLITALICOワークスやKaienといったプログラミングが学べる就労移行支援事業所や、ハローワークの職業訓練校で基礎を学ぶのが王道ルートです。基礎スキルさえ身につければ、dodaチャレンジがあなたのレベルに合った未経験歓迎の優良求人を必ず見つけてくれます。
それは、もはや過去の話です。確かに数年前まではそうした傾向もありましたが、今は全く違います。IT業界は徹底した実力主義の世界。入社後にスキルと実績を示せば、障害の有無に関わらず、一般雇用の社員と完全に同等の評価や昇給を得られます。実際に、障害者雇用で入社し、チームリーダーや専門職として年収600万円以上を得ている方は珍しくありません。大切なのは、無理なく安定して働き続け、着実に実績を積むこと。そのための最高の環境を手に入れるのが、障害者雇用の最大のメリットなのです。
まとめ:あなたの未来は、今日の「たった一つの行動」で変わる
障害は、あなたの可能性を閉ざす壁ではありません。むしろ、その経験があなたを、他の誰にも真似できない、深みと価値のあるエンジニアへと成長させる翼になります。
もう一人で、孤独と不安の中で戦う必要はありません。
あなたの隣には、障害者雇用のプロフェッショナルがいます。あなたの痛みと希望を深く理解し、あなたのキャリアを自分のことのように真剣に考え、あなたに最適な光の射す道を力強く指し示してくれます。
その、日本で最も頼りになるパートナーこそが、dodaチャレンジです。
登録はわずか60秒。もちろん、費用は一切かかりません。あなたが失うものは、何もありません。
しかし、この小さな一歩を踏み出すことで、あなたは絶望的な「今」を抜け出し、想像もしなかった希望に満ちた「未来」を手に入れることができます。
さあ、あなたの才能と個性を必要としている企業が、あなたとの出会いを今か今かと待っています。