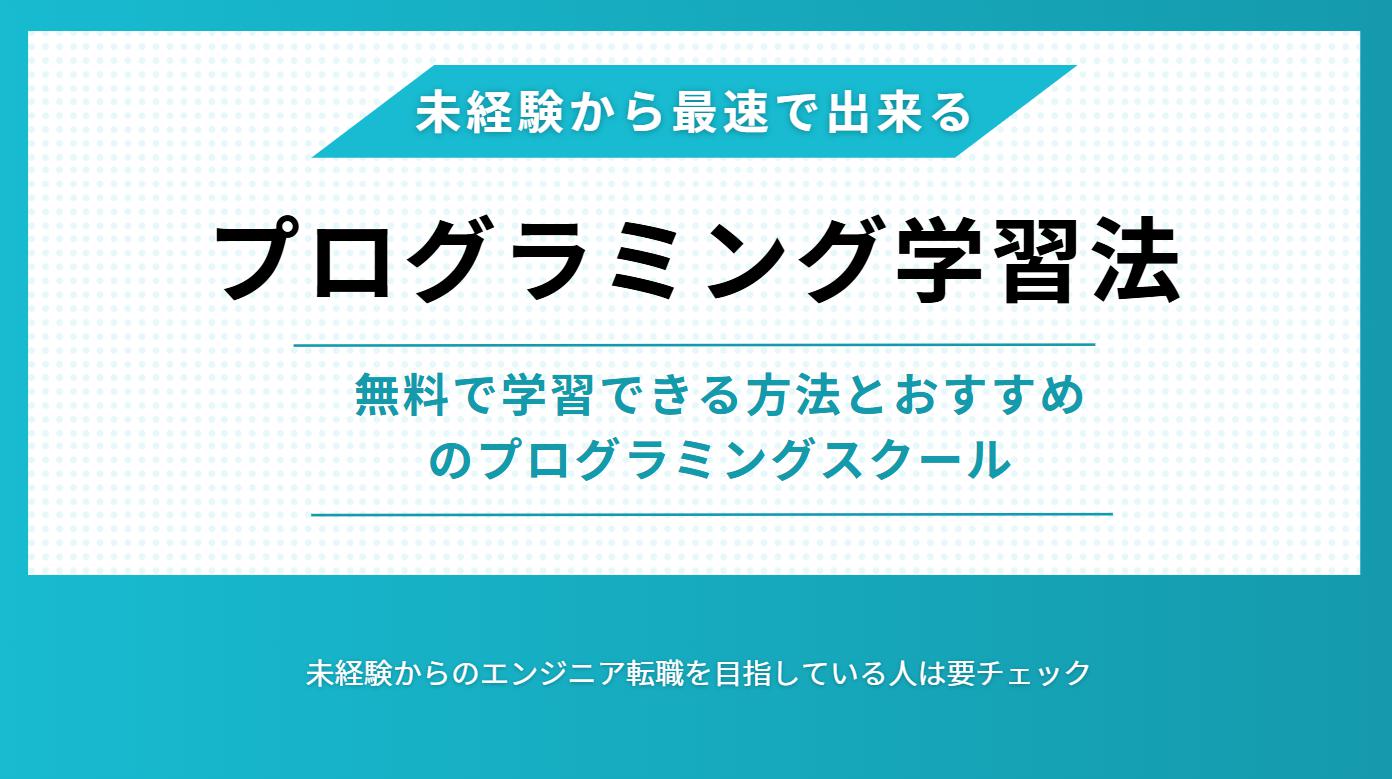#ITエンジニアとして働いているあなたは、今の職場環境に満足していますか?
「給与が見合わない」「残業が多すぎる」「成長を実感できない」など、モヤモヤした気持ちを抱えながら日々の業務に向き合っているのではないでしょうか。実は、多くのエンジニアが同じような悩みを抱えています。
本記事では、2025年最新の調査データを基に、エンジニアが抱える職場の不満TOP5と、それぞれの具体的な解決策を詳しく解説します。
目次
エンジニアの職場不満の実態|2025年最新調査から見える現実
株式会社ベイジが実施した「ITエンジニアの転職実態調査(2025年版)」によると、エンジニアの約7割が何らかの職場不満を抱えていることが明らかになりました。特に注目すべきは、転職を考える主な動機として「給与への不満」が41.68%と圧倒的に多く、次いで「仕事量・残業時間」が35.01%、「人間関係」が26.34%という結果が出ています。
これらの数字は、IT業界の構造的な問題を浮き彫りにしています。技術革新のスピードが速く、常に新しいスキルの習得が求められる一方で、それに見合った評価や待遇が得られていないという現実があります。また、慢性的な人材不足により、一人当たりの業務負荷が増大している状況も見逃せません。
・転職経験のあるエンジニアは全体の68.4%
・転職先の7割以上が事業会社(SIerからの転職が増加)
・平均転職回数は2.3回(キャリアチェンジが一般化)
・転職後の年収アップ率は平均23.5%
しかし、ここで重要なのは、不満を抱えたまま我慢し続ける必要はないということです。適切な対策を講じることで、現在の職場での状況を改善したり、より良い環境への転職を実現したりすることは十分可能です。
第1位:給与が低い・昇給が見込めない(41.68%)
エンジニアの職場不満の第1位は「給与の低さ」です。ITエンジニアの平均年収は約550万円と他職種より高い傾向にありますが、専門性の高さや市場価値を考慮すると、多くのエンジニアが「正当に評価されていない」と感じています。
なぜエンジニアの給与問題が起きるのか
給与問題の背景には、日本企業特有の年功序列制度と、エンジニアのスキル評価の難しさがあります。技術力の高いエンジニアでも、勤続年数が短ければ給与が低く抑えられるケースが多く、これが特に20代〜30代のエンジニアの不満につながっています。
- 年功序列により、スキルや成果が給与に反映されにくい構造
- エンジニアの専門性を正しく評価できる人事制度の不在
- SIer業界特有の多重下請け構造による中間マージンの問題
- 経営層のIT投資に対する理解不足
社内で実践できる給与改善アプローチ
まず試すべきは、現在の職場での改善策です。多くのエンジニアが「言っても無駄」と諦めていますが、適切なアプローチを取れば、昇給の可能性は十分にあります。
1. データに基づく昇給交渉の準備
感情的な訴えではなく、客観的なデータを用いた交渉が効果的です。自身の市場価値を示す転職サイトの年収診断結果、同業他社の給与水準、自身の成果を数値化したレポートなどを準備しましょう。特に、プロジェクトの成功による売上貢献額や、効率化による工数削減効果を具体的な金額で示すことが重要です。
2. 評価制度を活用したスキルアップ戦略
会社の評価制度で重視される項目を把握し、戦略的にスキルを習得します。技術スキルだけでなく、マネジメント能力や顧客折衝力なども評価対象となることが多いため、これらの能力開発にも注力しましょう。
転職による年収アップの現実的な戦略
社内での改善が難しい場合、転職は有効な選択肢となります。ただし、2022年後半から「エンジニアバブル」が終焉し、以前のような大幅な年収アップは期待しにくくなっています。
1. 事業会社への転職を検討:DX推進により、事業会社のエンジニア需要が高まっています
2. 希少性の高いスキルセットを構築:AI/機械学習、クラウドアーキテクチャ、セキュリティなど
3. ポジションアップを狙う:テックリードやエンジニアリングマネージャーなど
4. 成長企業を見極める:資金調達情報や事業成長率をチェック
第2位:仕事量が多い・残業時間が長い(35.01%)
「毎日終電まで働いている」「休日出勤が当たり前」といった過重労働は、エンジニアの心身の健康を蝕む深刻な問題です。特にプロジェクトの納期前は、月80時間を超える残業も珍しくありません。
エンジニアの長時間労働が生まれる構造的要因
ITエンジニアの残業が多くなる背景には、業界特有の事情があります。開発作業は区切りをつけにくく、「あと少しで完成」という状況が続きやすいのです。また、突発的なシステム障害への対応や、クライアントからの仕様変更要求など、計画外の作業が頻繁に発生します。
- 見積もりの甘さによる問題
営業部門が受注を優先し、実現困難な納期で契約してしまうケースが多く、現場のエンジニアにしわ寄せが来ます。 - 人材不足による個人への負荷集中
優秀なエンジニアほど多くのプロジェクトを掛け持ちすることになり、業務が集中する傾向があります。 - 非効率な会議やドキュメント作成
本来の開発業務以外に、形式的な会議や過剰なドキュメント作成に時間を取られることも問題です。
今すぐできる業務負荷軽減の実践方法
タスクの可視化と優先順位付け
まず、自身が抱えているタスクをすべて書き出し、重要度と緊急度でマトリクス分類します。そして、本当に自分がやるべき業務なのか、他の人に任せられないか、そもそも不要ではないかを検討します。この「タスクの棚卸し」を月1回行うだけでも、業務効率は大きく改善します。
「No」と言える関係性の構築
新規の依頼に対して、「できません」ではなく「代替案」を提示することが重要です。例えば、「この機能を実装するなら、納期を2週間延ばす必要があります」「Aの作業を優先する場合、Bは来月に回します」といった具体的な提案により、建設的な調整が可能になります。
働き方改革が進んでいる企業の見極め方
転職を検討する場合、本当に働き方改革が進んでいる企業を見極める必要があります。採用サイトの情報だけでなく、以下の点を確認しましょう。
- 平均残業時間の具体的な数値(月平均20時間以下が理想的)
- フレックスタイム制やリモートワークの実施状況と利用率
- 有給休暇の取得率(70%以上が望ましい)
- エンジニアの在籍年数と離職率
- 開発プロセスの効率化への取り組み(アジャイル開発、CI/CDの導入など)
第3位:人間関係が悪い・社内政治に疲れた(26.34%)
「高圧的な上司」「協力的でないチームメンバー」「派閥争い」など、人間関係の問題は精神的なストレスの大きな要因です。技術力があっても、人間関係が原因で実力を発揮できないエンジニアは少なくありません。
エンジニア特有の人間関係の課題
エンジニアの職場では、技術的な議論が感情的な対立に発展しやすいという特徴があります。プログラミング言語やフレームワークの選定、設計思想の違いなど、正解が一つではない問題について、互いの主張を譲らず関係が悪化するケースがよく見られます。
また、コミュニケーションスタイルの違いも問題になります。論理的思考を重視するエンジニアと、感情的なコミュニケーションを好む営業部門との間で、意思疎通がうまくいかないことも多いのです。
職場の人間関係を改善する心理学的アプローチ
アサーティブコミュニケーションの実践
相手を否定せず、かつ自分の意見もしっかり伝える「アサーティブコミュニケーション」は、エンジニアの職場で特に有効です。「あなたの考えは理解できます。一方で、私はこう考えています」という形で、対立ではなく対話を促進します。
心理的安全性の醸成
チーム内で失敗を恐れずに発言できる環境を作ることが重要です。自ら率先して「分からないこと」を質問したり、小さなミスを共有したりすることで、心理的安全性の高いチーム文化を築いていきます。
・毎朝の挨拶を欠かさない(名前を呼んで挨拶する)
・週1回は雑談の時間を作る(技術以外の話題も大切)
・感謝の言葉を具体的に伝える(「○○のおかげで助かりました」)
・1on1ミーティングで本音を話し合う
・チームビルディングイベントへの積極的な参加
転職時に良好な人間関係の職場を見つける方法
面接では技術的な質問だけでなく、チームの雰囲気や文化についても積極的に質問しましょう。「チームでの意思決定はどのように行われますか?」「エンジニア同士のコミュニケーションはどんな形で行われていますか?」といった質問から、職場の人間関係を推測できます。
また、カジュアル面談やオフィス見学の機会があれば、必ず活用しましょう。実際の職場の雰囲気や、社員同士のやり取りを観察することで、自分に合う環境かどうかを判断できます。
第4位:評価制度への不満・正当に評価されない(23.31%)
「頑張っても評価されない」「評価基準が不透明」という不満は、エンジニアのモチベーションを大きく低下させます。特に、技術的な貢献が数値化しにくいため、営業部門と比べて評価が低くなりがちという構造的な問題があります。
エンジニア評価の難しさと企業側の課題
多くの企業が採用している目標管理制度(MBO)は、エンジニアの評価には適していません。「バグを○件減らす」といった定量目標は、そもそもバグを作らないエンジニアが評価されないという矛盾を生みます。また、チーム開発において個人の貢献度を正確に測ることも困難です。
- 客先常駐エンジニアの評価問題
上司が現場にいないため、日々の働きぶりが見えず、適切な評価ができません。クライアントからの評価と社内評価にギャップが生じることもあります。 - 技術力と事業貢献のバランス
高い技術力を持っていても、それが直接的な売上に結びつかない場合、評価が低くなる傾向があります。 - 評価者の技術理解不足
非エンジニアの管理職が評価を行う場合、技術的な難易度や工夫を正しく理解できないことがあります。
評価を上げるための戦略的な自己アピール
成果の可視化と定期的な報告
自身の成果を数値やグラフで可視化し、定期的に上司に報告することが重要です。「システムの応答速度を50%改善」「コードレビューで○件の潜在バグを発見」など、具体的な数値で貢献度を示すことで、評価者も判断しやすくなります。
評価面談での効果的なプレゼンテーション
評価面談では、単に成果を羅列するのではなく、ストーリー性を持たせて伝えます。「課題→解決策→実行→成果→今後の展望」という流れで説明することで、あなたの思考プロセスと成長が伝わりやすくなります。
透明性の高い評価制度を持つ企業の特徴
転職先を選ぶ際は、以下のような評価制度を持つ企業を探しましょう。
- スキルマップやコンピテンシーモデルが明確に定義されている
- 360度評価やピアレビューを導入している
- 技術職向けのキャリアラダーが整備されている
- 評価のフィードバックが具体的で改善点が明確
- エンジニア出身の評価者がいる、または技術顧問が評価に関与している
第5位:仕事にやりがいを感じない・成長機会がない(44.71%)
意外なことに、転職先に期待することの第1位は「仕事のやりがい」(44.71%)で、給与や労働時間を上回っています。単調な保守作業の繰り返しや、レガシーシステムの維持ばかりでは、エンジニアとしての成長を実感できません。
エンジニアのやりがいを奪う環境要因
やりがいの喪失は、以下のような環境で起こりやすくなります。技術的なチャレンジがない、新しい技術を学ぶ機会がない、自分の仕事が誰の役に立っているか実感できない、といった状況が続くと、エンジニアとしてのアイデンティティが揺らいでしまいます。
1. 技術的停滞:5年以上同じ技術スタックで、新しい学びがない
2. 裁量権の欠如:すべて上からの指示で、自分で考える余地がない
3. フィードバックの不在:作ったものがどう使われているか分からない
4. 成長の頭打ち:これ以上スキルアップしても評価や役割が変わらない
現職でやりがいを取り戻す方法
社内プロジェクトの立ち上げ
業務効率化ツールの開発や、社内勉強会の企画など、自主的なプロジェクトを立ち上げることで、やりがいを創出できます。小さくても良いので、自分が「面白い」と思えることから始めるのがポイントです。
オープンソースへの貢献
業務時間外にはなりますが、オープンソースプロジェクトへの貢献は、技術力向上とやりがいの両方を得られる excellent な方法です。GitHubでの活動は、転職時のアピール材料にもなります。
メンタリングやナレッジシェア
後輩エンジニアの育成や、技術ブログの執筆など、知識を共有する活動もやりがいにつながります。教えることで自分の理解も深まり、新たな気づきを得られることも多いでしょう。
成長機会の多い企業を見極めるポイント
転職で成長機会を求める場合、以下の点に注目しましょう。
- 技術スタックが現代的で、定期的にアップデートされている
- 研修制度や資格取得支援が充実している
- カンファレンス参加や技術書購入の補助がある
- 20%ルールなど、自主的な技術研究の時間が確保されている
- 技術的な意思決定にエンジニアが関与できる文化がある
転職を成功させるための戦略的アプローチ
ここまで各不満に対する解決策を見てきましたが、最終的に転職を決断する場合、成功確率を高めるための戦略的なアプローチが必要です。
2025年の転職市場の現実を理解する
まず認識すべきは、「エンジニアバブル」は終焉したという現実です。2022年後半から市場は大きく変化し、以前のような「転職すれば誰でも年収が上がる」時代は終わりました。特に経験の浅いジュニアエンジニアにとっては、厳しい市場環境となっています。
一方で、AIやクラウド、セキュリティなど、特定分野の専門性を持つエンジニアの需要は依然として高く、これらのスキルを持つ人材は好条件での転職が可能です。重要なのは、自身の市場価値を客観的に把握し、現実的な目標設定をすることです。
効果的な転職活動の進め方
- スキルの棚卸しと市場価値の把握
まず、自身のスキルセットを整理し、転職サイトの年収診断ツールなどで市場価値を確認します。複数のツールを使い、平均値を取ることで、より正確な相場感を掴めます。 - キャリアの方向性を明確化
技術を極めるスペシャリスト路線か、マネジメント路線か、それとも特定領域のエキスパートを目指すか。5年後、10年後のキャリアビジョンを明確にしてから企業選びを始めましょう。 - 情報収集の多角化
企業の採用サイトだけでなく、口コミサイト(38.56%のエンジニアが活用)、技術ブログ、社員のSNS発信など、多角的に情報を収集します。特に、エンジニアのブログやQiita記事からは、技術スタックや開発文化がよく分かります。 - ポートフォリオの準備
GitHubでのコード公開、技術ブログ、登壇資料など、自身の技術力を示すポートフォリオを準備します。特に、実際に動くアプリケーションやツールがあると、評価が高くなります。
面接で確認すべき重要ポイント
面接は企業を評価する場でもあります。遠慮せずに以下の点を確認しましょう。
✓ 実際の残業時間と有給取得率
✓ 評価制度の詳細と昇給・昇格の実績
✓ 開発チームの体制と意思決定プロセス
✓ 技術的な課題と今後の技術戦略
✓ エンジニアのキャリアパス事例
✓ リモートワークやフレックスの実際の運用状況
✓ 研修制度や自己研鑽への支援内容
まとめ:不満を成長の機会に変える
エンジニアが抱える職場の不満TOP5(給与、労働時間、人間関係、評価制度、やりがい)は、いずれも深刻な問題ですが、適切なアプローチで改善可能です。重要なのは、不満を抱えたまま我慢し続けるのではなく、具体的な行動を起こすことです。
まずは現職での改善を試み、それが難しい場合は転職を視野に入れる。この順序で考えることで、より良いキャリアを築けます。ただし、2025年の転職市場は以前より厳しくなっているため、自身の市場価値を客観的に把握し、戦略的に行動することが成功の鍵となります。
最後に、職場の不満は「成長のサイン」でもあります。現状に満足できないということは、より高いレベルを目指す意欲がある証拠です。この記事で紹介した解決策を参考に、あなたらしいキャリアを築いていってください。エンジニアとしての充実した日々が送れることを願っています。
1. 自身の不満を具体的に書き出し、優先順位をつける
2. 社内で改善できることから着手する
3. スキルの棚卸しと市場価値の調査を行う
4. 必要に応じて転職エージェントに相談する
5. 長期的なキャリアプランを描き、逆算して行動する